今回紹介するのはコレ!
亀田達也さん著書の
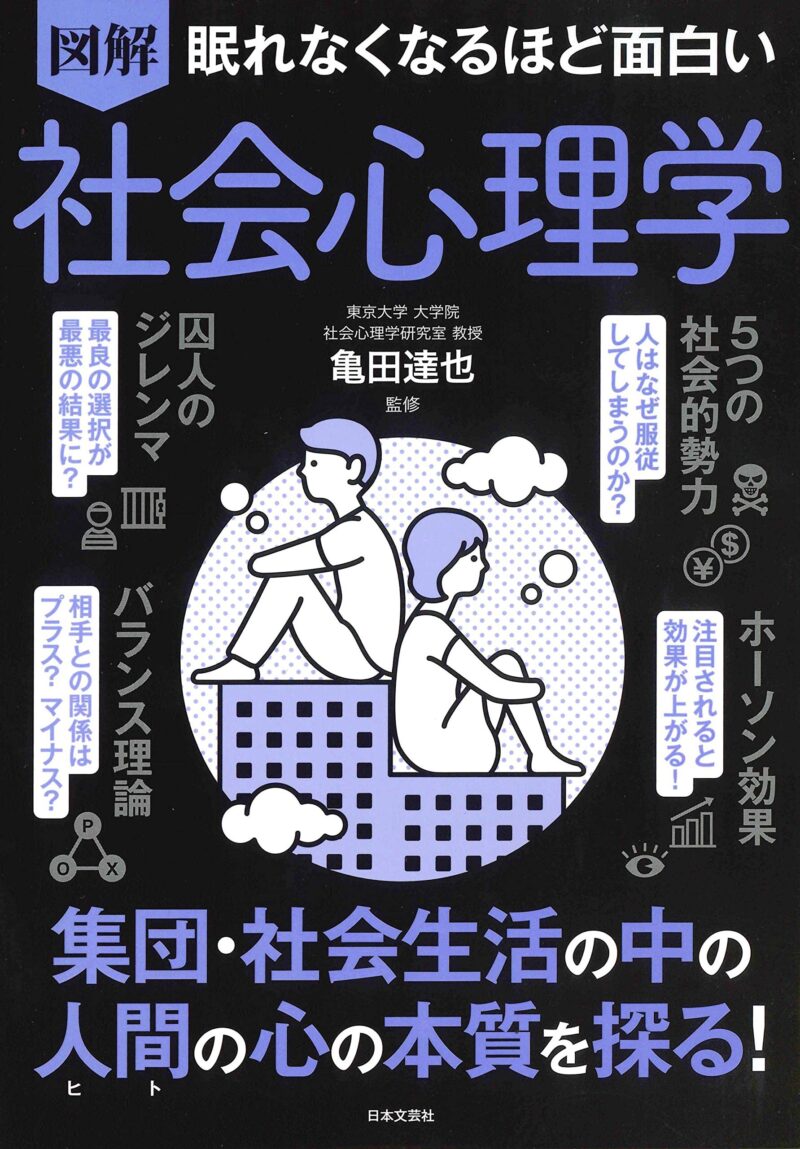
『眠れなくなるほどおもしろい社会心理学』
です!
今回も実用的な部分をピックアップして要約していきます!
では早速入っていきましょう!
ゲームや漫画は犯罪に影響する?
結論から言えばゲームや漫画で残虐性や暴力性が高いを見ると犯罪を犯す可能性が上がる!
これは、目で見た情報を自然に学習してしまう
『観察学習(モデリング)』
という心理状態が原因で、例えば攻撃的な映像を見た者は、その後、目で見た情報に影響され、攻撃的になりやすくなるのです!
また、実験の結果としては、女性より男性の方が影響されやすいことがわかっています!
また、この状態の対策もわかっており、犯罪や暴力の映像と同時に罰を受ける映像を見ると犯罪性や暴力性が抑制されることがわかっています!
あおり運転しやすい人の特徴!
2016年の調査で、全国のドライバーの54.5%があおり運転をされた経験があるそうです!
でもこのあおり運転も社会心理学が強く関わっており、あおり運転をしやすい人の特徴もわかっています!
単純に短気な方がしやすいという訳ではなく、
『敵意帰属バイアス』
が強い人があおり運転をしやすいことが分かっています!
これは簡単に言えば『相手からされた行為がたとえわざとで無かったとしても、自分に敵意や害意がある』と感じてしまう心理状態です!
普段から、相手の行動に敵意を感じてしまう方は一度考える時間を作り、相手の行動に敵意を感じないようにしましょう!
ネット炎上は何故起きる?
『社会比較説』・・・他者の多くが自分と同じ意見であることで自信を持ち、その考えが強化されること!
ネット上では多数の意見が存在する!勿論自分と同じ意見も存在する!そして、ここで怖いのは、自分の意見が何より正しいと思ってしまい、違う意見を攻撃してしまうところにある!
この心理状態こそが『ネット炎上』となって現れる!
渋谷ハロウィン事件の原因は?
ハロウィンや多数の人が集まる状態では、普段だったら絶対にしないのにやってしまうという
『群衆心理』
が働き、冷静な判断が出来ていれば絶対にしないのに、トラックをひっくり返したりして周りに迷惑をかけてしまう!
人はなぜ組織に弱い!
組織が持つ5つの勢力が個人に対して働き、人を服従させてしまう!
①報酬勢力
→報酬を与えることで服従を促す!
②正当勢力
→上司や先輩など目上の立場を利用する!
③参照勢力
→相手の行為を利用する!
④強制勢力
→罰を与えることで、相手を服従させる!
⑤専門勢力
→専門家であることで、相手を服従させる!
これらの勢力に影響されると、その組織の意見が、間違っていたとしても同調してしまう
『外面的同調』
ということ状態に陥ってしまう!
組織での間違った意見の発生条件!
組織の意見が個人を上回るとは限らない!
個人だと正しい判断が出来るのに、集団になると間違った判断してしまう事を
『集団的浅慮』
というのだが、この状態が発生するには3つの条件がある!
①無根拠な自信
②外部からの忠告の軽視
③反対意見の遮断
これらの兆候が出来たら、その組織は要注意です!
また、組織の場合間違った事を言ったとしても中々覆せなくなってしまう
『心理的拘泥現象』
という状態に陥る!
このように前もって間違った意見を出す前に、話し合いの場に予め反対意見を出すメンバーを決めておく
『悪魔の擁護者』
という方法が効果的で、組織の方向性を正しい方へ導いてくれる!
集団会議での弊害!
集団で行う会議である程、自分のアイデアや意見を良いタイミングで発言しにくくなる為、個人の能力をフルに使えなくなる事がある!これを
『プロセス・ロス』
という!
会議を時間内に終わらせる事も大事だが、自由発言する時間を取れないと感じるならば、会議前に会議中に思いついたアイデアなどはその時に書き留めて貰い、後でそれについて話す時間を作る方といった対処をとれば問題はない!
集団対立は親睦会ではなくミッション!
集団単位の対立では、食事会や親睦会などのイベントで仲良くなることは無い!下手すれば親睦会の中で余計に仲が悪くなる可能性もある!
そんな時に有効なのが、各集団が協力しないと達成出来ないミッションを与えるのがいい!
二つの対立する集団を無理に仲良くさせる必要は無い!でも、協力した方がメリットが高いと感じさせれば、自然と無駄な対立は自然と解消される!
少数派が多数派の意見を変えるには?
少数派が多数派の意見を変える事は容易では無い!しかし、多数派が心変わりしやすいという状況というのは社会心理学の研究で解明されている!
その条件が2つあり、
①一貫性がある事
②多数派と共通点がある事
である!
一貫性があることで説得力があり、共通点がある事で、反対意見という『敵』から『味方』という風に認識が変わる為、意見を受け入れて貰いやすくなる!
小さいお願いは大きなお願いの種!
人は段階的に受け入れやすい要求から、徐々に大きな要求をすると承諾を得やすくなる、
『フット・インザ・ドア・テクニック』
という方法がある!
なぜこのような状態に陥るかというと、小さい要求を受け入れた時に、自分が良いと感じた要求は受け入れるべき!という一貫性を持ちたい心理が働き、大きな要求も呑んでしまうという
『一貫性欲求』
が働くからである!
例えば、そこまで好きでもない相手と一夜を過ごしたあと、好きではないけど、一夜をともにしたという矛盾を解決する為に、好きになってしまう!という心理状態もこの一貫性欲求からくるものである!
良い人間関係が生産性を上げる!
人が生産性を上げるには、人間関係が重要だということが実験で分かっている!
そして、良い人間関係とは2種類あり、
①上司、部下というフォーマルな関係ではなく、仲間というインフォーマルな人間関係!
②定期的に自分の意見や不満を聞いてくれる職場!
特に、②にあっては、労働条件が悪くなったり、賃金が下がったとしても、生産が上がるという事が実験で証明された!
環境が悪かったり、賃金が安かったとしても、自分の意見をしっかり聞いてくれたり、不満を聞いてくれる環境や人がいれば、生産性は上がるのである!
やる気が無くなる報酬!
これをしている時は楽しい!や達成感などを感じるなどの内発的動機づけがある状態で、その作業に対して報酬を用意すると、その『報酬』という外発的動機づけにより、人はやる気を失ってしまう!この心理状態を、
『アンダーマイニング現象』
という!
好きな事を仕事にした途端、やる気が無くなってしまうのも、好きでやっていたことが、お金を稼ぐためという外発的動機づけに変わってしまう為、人はやる気を失ってしまう!
人の「ものさし」はいつも自分!
人には人それぞれの考え方や捉え方があると心の中ではわかっていても、自分の意見や行動が最も一般的である!と考えてしまう現象を、
『フォールス・コンセンサス現象』
という!
人に何かプレゼントをした時に、自分が渡したのだから、相手も渡してくれるだろう!という心理状態もこの現象で起きることであり、もし、自分の考え方と違う考え方を示した時は、その事に対して反発したりしてしまう状態に陥りやすい為、注意が必要である!
人は時に不合理な判断をする!
2つの物事では合理的な判断が出来るのに、1つの「おとり」を用意すると、人は時に不合理な判断をしてしまう!
ある実験で、
①WEB資料が年間59ドル
②紙資料が年間125ドル
③WEB +紙資料で125ドル
という3拓で、どれを選ぶか?という実験で多くが③を選んでしまった!
同じ資料という点を理解出来ていれば、本来なら①か効率的だと分かるのに、③という「おとり」を用意することで、正確な判断が出来なくなってしまい、不合理な判断をしてしまう事がある!この心理状態を
『おとり効果』
という!
何かサービスや物を売る時もこの心理状態を活かせば、上手く売れるかもしれない!
所属することで人は存在を認識する!
〇〇高校出身や〇〇スポーツをしているなどのカテゴリーの集団にいる!と自己認識をすることで、自分の存在をより確認できるといった心理状態を
『社会的アイデンティティ』
という!
人がスポーツなどで、自分の好きなチームや選手に熱狂してしまうのも、その同じものがが好きだといチームに所属することで、自分の存在を自己確認できるため、余計にのめり込んでしまう!
人が納得する為の4つの過程!
人が自分と違う考えや新しい意見などを聞いて納得するためには4つの過程が必要であることがわかっている!
①注意-その意見に対して注目させる!
②理解-その内容について理解する!
③受容-その意見を受け入れる!
④記憶-その意見を継続的に保持する!
この4つの過程を意識して説得するだけでも、相手を納得させる可能性は上がるが、更に、説得する為の技法があり、相手に専門知識が無い場合は、とにかく良い面だけを話す
『一面性メッセージ』
が有効で、相手にとある程度知識がある場合は、良い面と悪い面の両方を話す、
『両面性メッセージ』
が良いとされる!
また、その意見が相手に及ぼす影響が大きければ大きいほど、反対の意見や行動を助長してしまう、この心理状態を
『心理的リアクタンス』
と言い、相手を納得させるにはあまり相手に影響が無いような内容で説明した方が説得させやすい!
最後に!
普段ニュースで流れているあらゆる事件であったり、SNSのバズったりするのも、全てこの社会心理学が絡んできます!
いつもであれば何も感じないと思いますが、この社会心理学をある程度理解することで、なんでこんな状態になったんだろう?
もしかしたら、こんな心理状態でこうなったのかな?と自分の中で仮説を立てられるようになるので、今特に取り上げられている
『自分で考える力』
を身につけることができます!
また、仕事や家庭においても、社会心理学を理解していれば、無駄に孤独を感じたり、過度に組織に依存することも減ってくるので、日常を暮らす上で、精神的楽になれます!
この本では、一つの心理状態について文章での説明のあとに、イラスト付きの説明書きがあるので、読んでいてもわかりやすい内容の本でした!
でも、中にはあまり日常生活においてあまり使えない心理状態の説明もあったので、多くある事例の中から自分に必要なものをピックアップする!といった使い方が向いている本だと思いました!

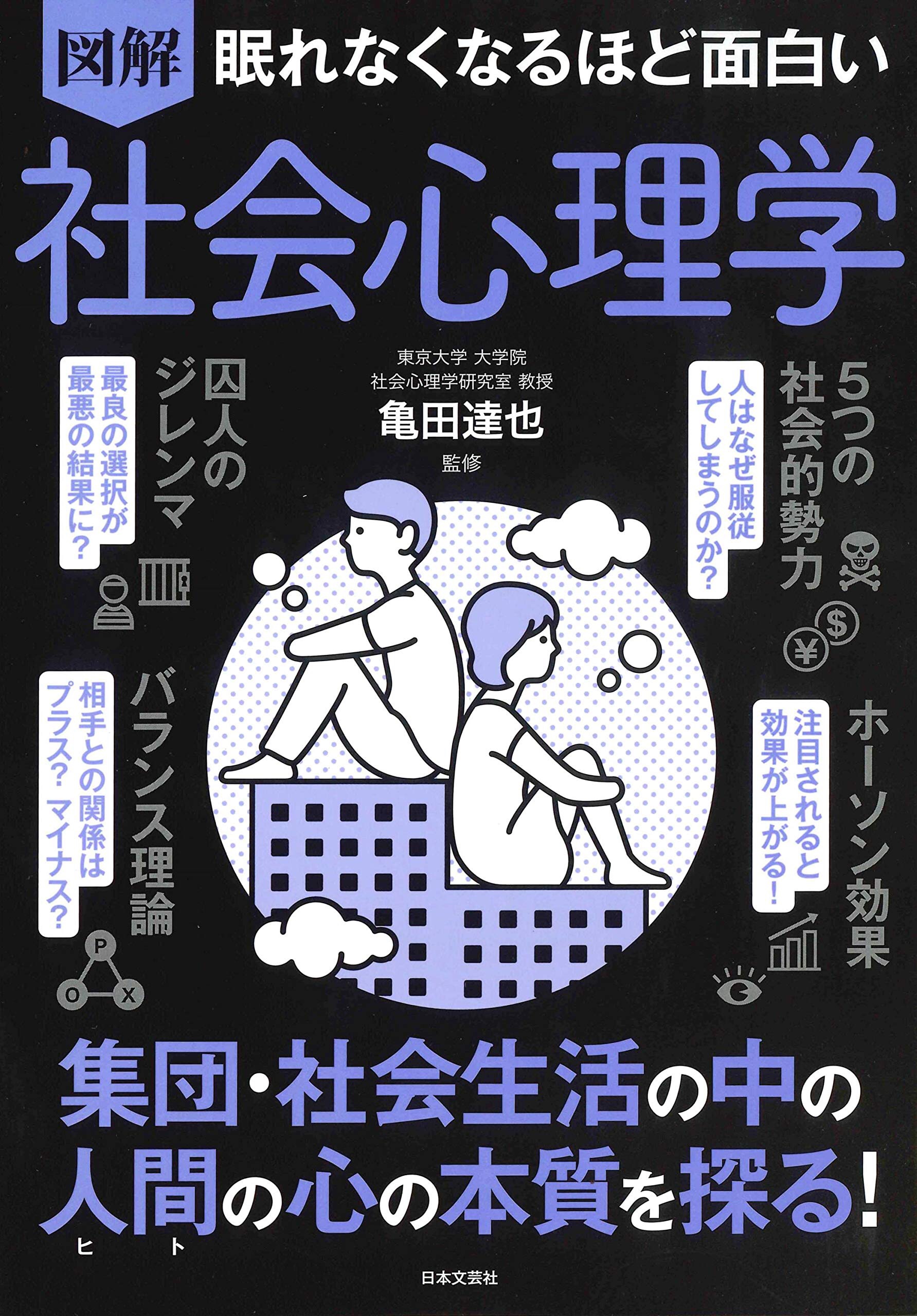


コメント